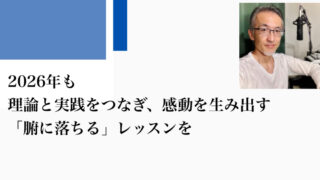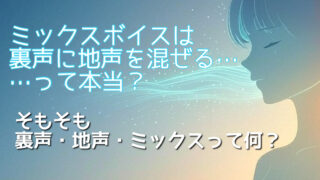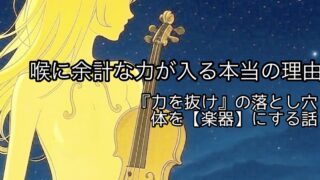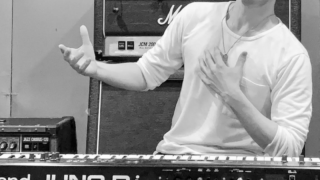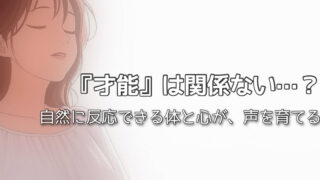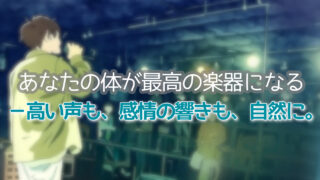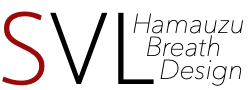鼻腔共鳴──ボイトレに通った方、声楽を習ったことがある方なら、一度は聞いたことがある言葉でしょう。
「響きが増す」「声が通るようになる」──そんな期待を抱いて、鼻腔共鳴に取り組んだ方も多いはずです。
ですが、本当の意味での基礎を体得しないまま、共鳴ばかりに意識が向くと、むしろ発声や表現を崩してしまうことさえあります。
本記事では、なぜ“鼻腔共鳴から始めてはいけないのか”、その理由を私のボイストレーニングにおける根幹でもある、「自然で普通の声=ゼロの声」という視点から解説します。
ゼロの声とは、まだ音程や芯すら持たない、しかし確かな土台となる声であり、ミックスボイス習得の第一歩でもあります。
序章:なぜ鼻腔共鳴から始めてはいけないのか
「鼻腔共鳴を使いなさい」「もっと鼻を響かせて」。お決まりと言っていいほど、必ず出てくるアドバイスですが、多くの人は、やり方がわからないか、やり方を教わったところでうまくいきません。
「共鳴ってこれで合ってるの?」「ただの鼻声かも?」と、戸惑ったことがある方、またこれから始める方も、共鳴の前にあるものを知っておいて欲しいのです。
──それは、“自然な普通の声”という基礎の基礎である、スタートラインの声ができていないからです。
基礎という前提条件なしに、その上に基本や技術という建物は建てられないのです。
1. 普通の声とは何か──“ゼロの声”の正体
思わず出る自然な声
それは、立派でもなく、大きくもない、でも誰かに届く自然な声。たとえば、感動したときに漏れるような一言や、静かに語りかけるような声。それが、表現のすべての出発点です。
これはボイトレ業界でよく聞く、ミックスボイスとも関係しています。
しかし、ミックスボイスについても大きな誤解があります。
以下の参考記事で詳しく解説しています。
思わず出る声とミックスボイスの関係も解説。
ミックスボイスとは基礎ができた時に最初に出る自然な声、と覚えておけば間違いありません。
究極の自然な普通の声=ゼロの声とは
自然に反応して、思わず出る声の中でも、声が生まれる瞬間が誰にも気づかれないくらい自然に出る声のことです。
いつ鳴り始めたか分からないほどスムーズなフェードイン──それが「ゼロの声」。
ジャンルも立派さも、音程すら感じさせない、究極の“自然な普通の声”です。
これは、体の楽器化と、呼吸圧と声帯のバランスが取れたとき、自然に立ち現れるものです。
ジャンルやテクニックにかかわらず、すべての声の基礎となる“無意識的な声”──
それがゼロの声であり、浜渦ボイトレメソッドの重要な基礎となります。
大きなキャンバスの中心にある点
この声は、体を大きなキャンバス=ホールと見立て、その中央にそっと筆を置くように生まれるもの。響かせよう、通そうとするほどに不自然になり、逆に届かなくなるのです。
不自然な普通の声・不自然で立派な声
「普通に話してるだけです」と言いながら、体を楽器化せず、ただ、その人にとっての普通の声を作っている状態──それは不自然な普通の声。そして、基礎を無視した立派な声も、やはり不自然な立派な声。
どちらも真の基礎とはかけ離れています。
動画で見る「思わず出る自然な声」の実例
思わず出る声から話すように歌い、歌うように話す方法を解説したボイトレ動画の決定版。
思わず出る音程も何もない声から、各ジャンルの声や、多くの方のモノマネ、話すときの波や間まで、実践解説しています。
第一線の方は、どんなジャンルのどんな声(裏声・地声・ハスキーボイス・ウイスパー・シャウト)でもゼロの声を持っていることもご理解いただけるボイトレ動画です。
■ 視聴者の声(YouTubeコメントより)
- 「唯一無二のボイトレ動画」
- 「YouTubeのボイトレ動画で1番本質的な話」
- 「わかりやすいです!」
- 「歌がうまくなる、喉の使い方うまくなる登竜門な動画!」
2. 声を支える“楽器”としての体づくり
楽器化とは何か
表現の出発点は、体を楽器にすること=体の楽器化。体が空間を持ち、あらゆる方向へ反応できる構えになってこそ、声が生きたものとなります。
キャンバスを崩さない呼吸=腹式呼吸の正体
体という楽器=キャンバスを壊さずに呼吸をする。この表現のためのこきゅうこそが、本当の腹式呼吸の始まりです。意識的に腹を動かすのではなく、空間の中を筆が動くように息が流れることで、自然に腹式となります。
体を楽器化して状態を維持することで始まる腹式呼吸は、意識してお腹動かすものとは、根本的に違うものなのです。
よく、手でお腹を押しながら「ハッハッハッ!」と声を出す練習がありますが、これは相当気をつけないと、なんとなくやっている気分を味わうだけで、効果はほとんどないのが実情です。
背筋や腹筋が「勝手に」動く体
「背筋を使え」「腹筋を使え」とよく言われますが、それらは意識して使うものではなく、声が自然に出た結果として使われているべきもの。基礎ができれば、筋肉は勝手に動き出すのです。
よくわからないまま意識して使おうとすると、誤った使い方が身についてしまったり、目的と関係なく使ってしまい、効果が全く得られないなど、むしろ逆効果になることもあります。
参考動画:体の楽器化と自動的に始まる腹式呼吸について
多くの方を迷わす、表現のための腹式呼吸の正体や、体を楽器にすることのへの理解が深まる動画を2本ご紹介します。
3. 共鳴は“自然に生まれる結果”である
鼻腔共鳴はその先にある
鼻腔共鳴は否定すべきものではありません。ただし、“自然な普通の声”ができていないうちは、意識しない方が良いです。順番が逆だと、鼻にこもった詰まった声、つまりただの鼻声になるだけです。
この鼻腔共鳴の失敗は、論理が発達した現代でも繰り返し起こっています。
私も当然、いろんな人から「共鳴、共鳴!」と言われ、ただただ苦しかった苦い思い出があります。
そこで多くの人がミックスボイスというものに飛びついてしまいます。
しかし、ミックスボイスこそ、基礎ができた時に最初に出る自然な声。
基礎ができれば、ミックスボイスは自動的についてくる。
その先に共鳴やいろんなテクニックが繋がっていくのです。
基礎や目的を理解しない、基本や技術はむしろ危険なのです。
共鳴はキャンバス内のクローズアップ
〇〇共鳴とは、広い体の中にある空間の、どこをクローズアップして使うかということ。中心をそっと押さえる“普通の声”があってこそ、共鳴は自然に生まれてくるのです。
4. 表現の誤解と“破綻する自由”
基礎をすっ飛ばすと何が起こるか
ジャンル的な声を真似したり、技巧だけを先に追いかけたりすると、小さなキャンバスに大きなものを無理やり描くような破綻が起こります。特に声楽では「立派さ=正しさ」という誤解が、いまだに根強くあります。
自由な表現とはルールの中の自由
「自由に歌えばいい」は一見もっともですが、体という楽器の秩序・呼吸の自然な流れの上に成り立つ自由でなければ、ただの自己満足になってしまいます。
5. 基礎が個性と上達を導く
“自然な普通の声”というゼロの声ができた人は、そこから勝手に上手くなっていきます。講師があれこれ指示しなくても、自分の感性に従って、個性ある表現へと育っていくのです。
キャンバスと筆と絵の関係がわかったということですから、あとは自由なのです。
つまり、個性と上達はワンセット。そしてその始まりこそが、“普通の声”を体から自然に出せるかどうかにかかっています。
基礎を教えるとは、感性と技術の種を渡すこと。
システムと最初の一歩がわかれば、どんどん上達するのは当然のことなのです。
それが浜渦メソッドの目指すものです。
逆に、本当の基礎を飛ばして、ただ呼吸法や発声法、共鳴やミックスボイスなどを何年習い続けても、自然で気持ちの伝わる歌、という本来の目的にはたどり着けないのです。