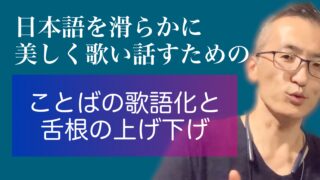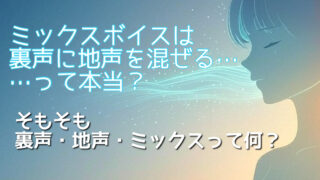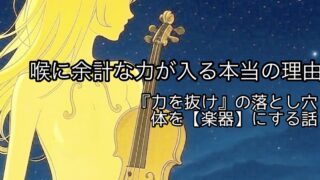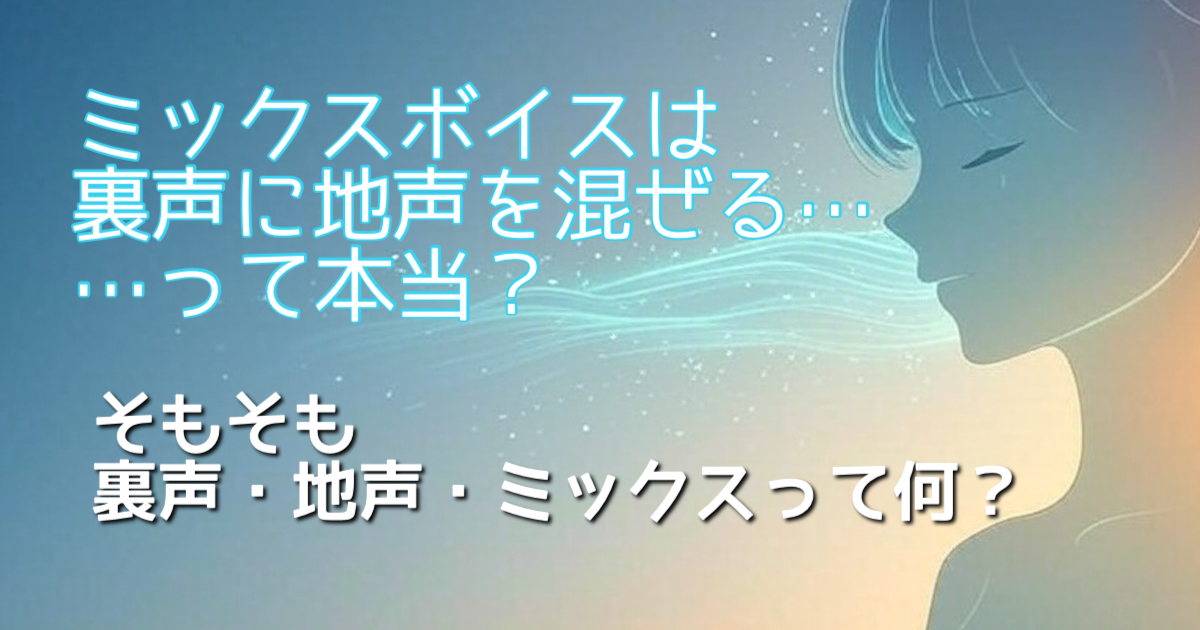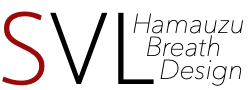「ミックスボイスって“裏声に地声を混ぜろ”って言われても、どうすればいいかわからない…」
「混ぜようとしても、途切れたり急に地声になったりしてしまう」
こんな声、よく耳にします。確かに「裏声に地声を混ぜろ」と教える人もいますが、これは危険な誤解を生むアドバイスです。
なぜなら、裏声には“地声が混ざる可能性の高いもの”と、“決して混ざらないもの”があるからです。混ざるものは自然にミックスにたどり着きますが、混ざらないものは無理に混ぜることはできません。
そもそも「混ぜる」という言い方自体が誤解の元」です。裏声と地声の間くらいだから、絵の具を混ぜるようにイメージしがちですが、実際には混ぜるものではありません。
裏声・地声とは何か?
声帯の厚さによって声は変わります。声帯が薄く、振動が首や胸に伝わらないのが裏声、少し厚く閉じ、振動が伝わるのが地声です。
しかし、声帯は意識して動かすことはできません。意識ではなく想像力で反応させるものです。だから私たちが整えるのは、声帯が自然に働く体=楽器化なのです。
体の楽器化で声帯・横隔膜が自由に
体を楽器として整えるとは、口腔・気道・肺などの空間を一体として開いたまま保つこと。空間を縮めたり固めず、一体化することで声帯や横隔膜は自由に動き、音色・強弱・息遣い・感情を自然に表現できます。
動画で詳しく解説しています:体の楽器化と声の関係
「混ぜる」のではなく、声帯の通過点としての声
楽器化された体の中で声帯が自然に働くと、裏声 → ミックス → 地声へ自然に移行できます。つまり、ミックスボイスは声帯の厚さの中間の声であり、特殊な声ではなく、普通の声の一部です。
- 裏声から少し厚くなった状態
- 地声から少し薄くなった状態
この中間で生まれる声が、ミックスボイスの正体です。
結論:ミックスボイスは「普通の声」
- 🎯 ミックスボイスは、体が整った人から自然に出る普通の声
- 🎯 裏声・地声を混ぜるのではなく、自由に行き来できる中間の声
- 🎯 本質は「体の楽器化」であり、声の分類ではない
この最初の基礎を作ることで、強い声、高い声も自然に出せるようになります。
関連記事・次のステップ