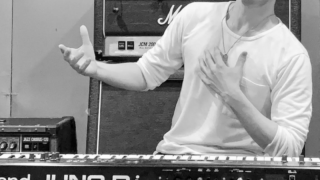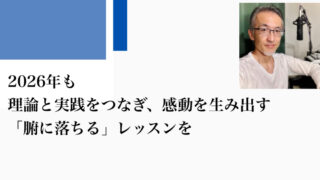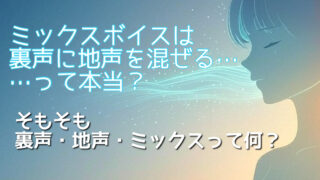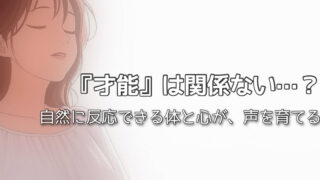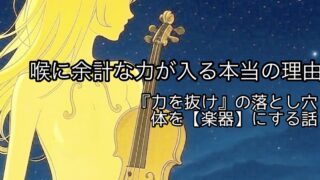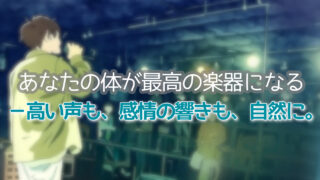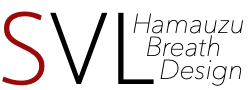何事にも動じない、全体を俯瞰(ふかん)する冷静さを持ちつつ、
その中で、喜びや怒り、悲しみなどの感情を自由に動かす。
一見すると矛盾しているようですが、これこそが自由で自在な表現のはじまりです。
そもそも俯瞰する力、「客観的な視野」という、「ありのまま」を受け入れるキャンバスがなければ、
喜びや怒りを出そうとしても、描き出す場所がないために、感情に“のまれて”しまう。
また、キャンバスが固定されずに、動いたり、崩れてしまうようでは、
どれだけ感情を持っていても、声や技術として現れることはありません。
練習が嘘をついてしまうのです。
自由な表現とは、技術を恣意的に使うだけではなく、それが自由に動く場所=受け皿があって初めて機能し、育つものなのです。
あなた自身の声や表現に、これまでとは違う何かを探している方──そんな方にこそ、この続きを読んでいただきたいと思います。
受け皿とは何か?
「俯瞰する視野」と言っても、精神論ではありません。
身体が閉じていては、そもそも自分の中に何も入ってこない。
体が開いてこそ、客観性が生まれる。
体が楽器として“開いている”からこそ、感情も情報も受け止められるのです。
つまり、体のキャンバス化=楽器化が必要なのです。
健全な精神は、やはり健全な肉体にしか宿りません。
受け皿とは、こういう構造です:
- 喜怒哀楽・主観に対して → 俯瞰・客観性という受け皿
- 基本や技術に対して → 身体という楽器(基礎)という受け皿
前者が後者を超えてしまうと、表現は破綻します。
また、後者が弱ければ、前者を小さく抑えるしかなくなります。
だから私はまず、「喜怒哀楽や技術を受け止められる器=身体と視野の土台=キャンバス」を育てることを、レッスンの核に置いています。
私がレッスンでお渡ししたいのは、どんな感情の起伏も、絶望も、そして技術も受け止め切るキャンバスです。
それがあれば必ず上達しますし、それがない技術や感情はうわべのものに過ぎないからです。
器の大きさが生む自由──犬と庭の関係に例えると…
キャンバスとは、表現のスケール感であり、その人の可能性そのものでもあります。
多くの人が、キャンバスが整っていないまま、
感情表現や滑舌、楽譜上の強弱といった「表面的な技術」に走ってしまう。
または、小さなスケールの中に自分を押し込めて、器用にまとめようとする。
しかし、器がないまま想いを盛ろうとしても、技術を載せようとしても、それは身につきません。小さくまとまるとそれはミニチュアです。
犬に大きな庭を与えれば、自由に8の字に走ることもあれば、
広いのに隅っこでうろうろしたり、犬小屋から出てこなかったりすることもある。
「それなら小さな庭で十分なのでは?」と思うかもしれませんが──そうではないのです。
大きな庭があるからこそ、その中の小さな動きにも庭という余白と動きの間に“コントラスト”が生まれ、意味を持つのです。
余白と動きのコントラスト。これこそが表現です。
器を作ると、「今から何かが生まれる」予感──静寂が生まれ、その空気感はお客さんに必ず伝わる。
だからこそ、どんなに小さな動きも、それは意味のある、深い表現となって伝わるのです。
器があり、そこに感情や声を受け止める表現があることで、
お客さんも「自分の感情を受け止めてもらえた」と感じてくれる──それこそが最高の瞬間です。
常に成り立つ関係性
表現において、こうあるべきバランスがあります:
- 楽器化された体 > 感情表現・技術
- 俯瞰 > 主観
前者が受け皿、後者がその中に表されるものです。
このバランスが崩れると、どれだけ練習しても、
表現は苦しくなり、うまくいかなくなってしまいます。
器の中に好きなものも“嫌なもの”も等価に受け入れられるか
多くのアーティストは、この受け皿と技術や声のバランスを取るために、
体と心、精神力と体力すべてを注ぎます。
それは、生きる実感そのものと向き合う行為でもあります。
しかしその代償も大きく、
バランスを崩せば、精神的に参ったり、燃え尽きてしまうこともある。
さらに難しいのは、器の中に“自分の嫌いなもの・苦手なもの”も入れなければならないこと。
人は、嫌なものを入れるくらいなら、器そのものを閉じてしまうものです。
レッスン中の緊張、嫌な相手、聞きたくない言葉……
そういうものを前にすると閉じてしまう感覚はお分かりだと思います。
どんなに気をつけていても、俯瞰する力が弱ると、嫌なものは受け入れられなくなる。
そういう時は休まなければなりませんが、多くのアーティストの悩みの根本でしょう。
俯瞰する力が増えれば増えるほど、感受性も強くなるということでもあるのです。
ですから、俯瞰の冷静さとは、ただ醒めて何も受け入れないのとは、むしろ真逆のことなのです。
個性とは「器の中身」ではなく、「器の広さ」
どんなに大きな器があっても、
自分のお気に入りのものばかりを入れていたら、表現の幅は限られます。
好きなものも嫌いなものも、等価に受け入れる。
その上で、喜怒哀楽や技術として活かしていく。
等価に受け入れるときに必要なのが、あらゆるものをありのままに見ること。
つまり主観でなく、客観的に、より多くのものを見て自分の中に受け入れることなのです。
つまり俯瞰する力です。
キレやすい人は、当然俯瞰ができていません。
スマホなどから気に入った情報だけを一方的に与えられていては、狭い器があっという間に埋まってしまい、自分の中から何も生まれなくなってしまいます。
それと歌の上達と、どんな関係があるのか?
もうお分かりかもしれません。
何があっても動じず受け入れる「楽器としての体=キャンバス」、
そしてそこに生まれる“想い”との間を埋めるものが技術です。
キャンバスがなければ、そもそも想いは生まれません。
想いもキャンバスもない技術は、「技術のための技術」です。
「脱力のための脱力」「共鳴のための共鳴」になってしまう。
結果として、人という体や精神が受け入れられず、
正しいことをやっているのに苦しかったり、上達しなかったり、
そこそこ歌えていても、何を伝えたいのかわからない歌になってしまうのです。
真面目な人も要注意。「正しいことをやれば結果がついてくる」ことを信じて、
正しい発声、正しい呼吸法、正しい発音、正しい音程と、正しさを追いかけて、
それを受けとめる受け皿を忘れてしまうことはよくあるのです。
正しいだけの表現には、余白がありません。
余白がないと、人は描いたものを認識できません。
それが窮屈な発声や表現に繋がってしまうのです。
楽器(体)と想いがあれば、技術はあとからついてくる。
キャンバスがあるから、そこに並べたものが、必要かどうか、何が足りないかがわかるんです。だから上手くなるんですよ。
そんなの精神論だって思う人もいるかもしれません。
いえいえ、これこそ本当の技術論です。
自分の体と精神の器、中で動かす横隔膜や声帯、感情などをコントロールするには、
論理的な思考がなければできないことなのです。
とりわけ、歌や演技はそういうものなのです。
それがあなたの本当の世界を切り開きます。
本当の表現の世界と、自分の表現、一緒に見てみませんか…♪
おすすめボイトレ動画【YouTube】
●【高音をズバッと出すコツ】自由な高い声は音色と音程の距離感で出す!【ボイトレの基礎】
高い声が苦手、出るけど出ているだけ、怖い、諦めた…そんな方へ、感情表現として意味のある本当の高い声を出すためのアドバイスです。
【チャンネル登録はこちらです】http://bit.ly/38pU0bd