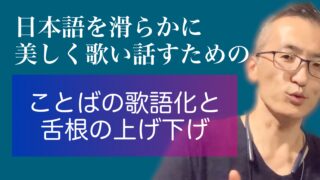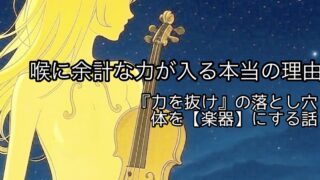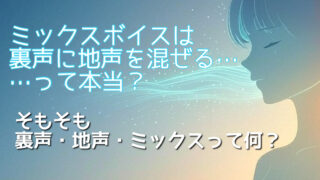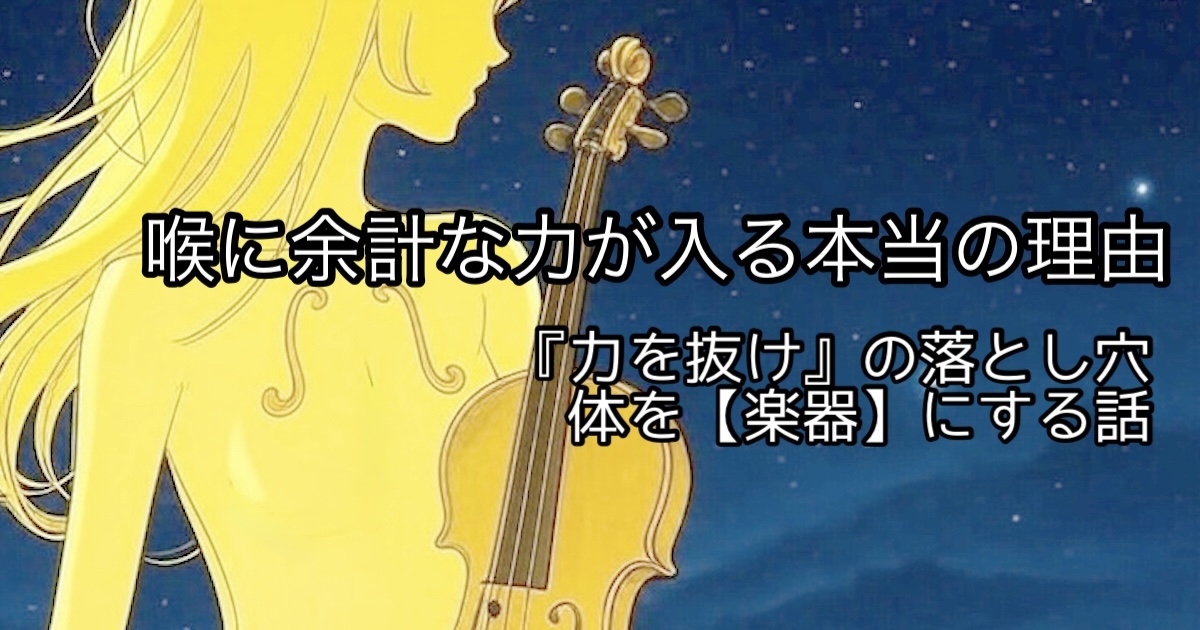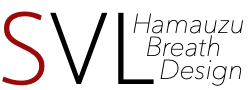「喉に力を入れないで」と言われても、どうすればいいのかわからない……。そんな経験はありませんか?
実はその“力の入れ方”や“抜き方”には、見落とされがちな構造的な落とし穴があるのです。
本記事では、「喉に力が入る本当の理由」と「何が間違っていて、何をすればよかったのか」を解き明かします。
単に“力を抜く”だけではうまくいかない理由、そして感動を伝える表現を可能にする「体全体を“楽器化”する鍵」まで、
浜渦ボイトレメソッドの視点から詳しく解説します。
2025年5月、本記事は完全リニューアルしました!
少し長くなりますが、ぜひお読み下さい。
喉に力が入る原因は「喉」じゃなかった?
「喉の力を抜いて」と言われたことがある方、多いのではないでしょうか。でも、言われてすぐできるなら苦労しませんよね。
かつての私もそうでした。
「喉に力なんて入れてない」と思っているのに、苦しい。
「力を抜いて」と言われても、「どうやって?」と聞けば、誰も明確に答えてくれない。
喉を意識して「脱力しよう」とするほど、むしろ力んでしまう。
いったい、なぜそんなことが起きるのでしょう?
「腹式呼吸ができていないから」「無理に声を出そうとしているから」──
そんな風に言われた経験がある方も多いかもしれません。
もちろん、呼吸法の未習得や、無理な発声が原因になることもあります。
しかし、問題の本質はもっと深いところにあります。
まず多いのが、
喉の力を抜こうとするあまり、体全体の支えまで失ってしまっているパターンです。
たとえば木管楽器の「リード」部分(音を鳴らす要)をしなやかにしようとして、
本体の楽器までフニャフニャにしてしまったら…当然、音は出ませんよね?
それでも無理に吹こうとすれば、「リードだけで音を出そうとする」──
つまり、「喉だけ」で声を出そうとするのと同じ状態になります。
楽器本体=体が置き去りにされているのです。
結果、声帯を過剰に使いすぎてしまい、響きが悪くなるだけでなく、声帯を壊す原因にもなります。
本人は「脱力しているつもり」。
でも、体の支えが消えてしまっているために、結果として、いつの間にか「喉だけ」に力が集まり、より固まってしまうのです。
本質は「体のバランス」にある
「体のバランスを取ること」は、実はとても難しいことです。
なぜなら、バランスが取れている人ほど、自分がどうやってバランスを取っているのか自覚がないため、
それを人に説明することができないからです。
逆に、理屈として構造を説明できる人であっても、
自身の体でそのバランスを実感できていなければ、指導も実を結びません。
この「できる人あるある」「できない人あるある」が、実は喉の力みに深く関係しているのです。
では、どうすれば?体の内側と外側の話
まず行うべきは、「内側」も「外側」もゆるめること。
– 外側=骨格・姿勢(=支えのフレーム)
– 内側=声帯、横隔膜、インナーマッスルなど
この「内と外」を同時に広げることが最初の一歩。
全身が風船のように、柔らかくふくらむイメージです。
その後、まず内側だけを少しずつ締めて、体内に圧力を作っていく。
ここが肝心です。
外側=姿勢や空間の広がりを保ったまま、
内側=内部に圧力を作る→声帯・呼気筋などだけを適度に働かせることで、
声帯は「薄く・しなやかに」閉じて振動する状態になります。
声帯にも、「外側の支え」と「内側の動き」という役割の違いがある──そう捉えると理解しやすくなります。
この時、体全体と接続された「外側」が広がっているからこそ、内側の声帯が自然にふわっと閉じる。
この「薄く出会った声帯」が振動すると、無理のない自然な発声が生まれるのです。
「そんなことできるの?」と感じた方へ。
できます。なぜならこれは、人が感動した時や深く納得した時に、無意識に起こっている身体反応だからです。
たとえば、何かに深く納得して、うなづきながら「なるほど…!」なんて言う時、
すでに多くの人は、無意識にこの流れを達成してしまっているんです。
つまり私たちが行っているのは、人間に本来備わっていた反応を、再び使えるようにするプロセスなのです。
それに、声・歌・演技といった表現を融合させていく。
これこそが浜渦メソッドの真髄です。
では具体的な実践方法を解説します。
【動画あり】息から声への自然なつながりを生む、4ステップの呼吸・発声法【最重要】
- 吸う=広げる(体の楽器化・スケールの大きさ)
体全体で空間を広げるように吸い、
肋骨・背中・骨盤底まで含めて柔らかく広げる。 - 圧縮する(気持ちの強さ)
広げたまま、内側から空気の密度を高めていく。
力むのではなく、“空気の重み”を感じるように。 - スプレーのように息を噴き出す(表現の呼吸)
沸騰したヤカンの笛や、風船から空気がシューっと出るように、
圧縮された息が細く、スプレーのように強く溢れ出す。
※この段階では、声帯はまだ関与していない。 - 声帯が「ふわっ」と捕まえる(表現を声に託す)
スプレーの圧がちょうど良くなった瞬間、
声帯が自然に振動し、声の発振と息が「重なる」
【重要ポイント】
順番ではなく、「バトンのリレー」のように“重なって”いくこと。
・広がりと圧縮が交差する
・圧縮とスプレーが重なる
・スプレーと声が交わる
= 広げたまま + 圧縮しながら + 吐きながら + 声を出す
→ すべてが共存する瞬間、それが「自然な声」です。
▼以下の動画では、この4ステップを実演しながら解説しています。
よくある失敗パターン
- 外側も一緒に締めてしまう
→ 声帯が「団子」のように固まり、振動できない - 団子になるので息が出ない
→ 声が止まる - 声が止まるから無理に息をぶつける
→ 息に圧がなく、喉が悲鳴を上げる - 無理にぶつけた息で喉がこじ開けられる
→ 一瞬声が出るが、すぐ枯れる - 焦ってさらに喉を閉める
→ また声が止まり、またぶつける…
この「負のスパイラル」に陥っている方が、とても多いのです。
本当の「脱力」は、意識ではなく構造から
喉の力は、本来、「歌う前」「話す前」には抜けている状態です。
でも、「さあ声を出そう」と思った瞬間に、外側までも緩めてしまっているのです。
その結果、支えを失った喉にだけ力が集まり、発声のたびに力んでしまう。
これが癖となって、「声を出す=喉を締める」という悪い習慣が身についてしまい。
これがひどくなって、声を出す前から喉を締めてしまう人も多いのです。
だからこそ必要なのは、ただの脱力ではなく、「広がり」と「内側のしなやかな締まり」なのです。
最後に
ここまで述べてきたこと──呼吸や発声法の前提にある、体の構造・バランス・順序・スムーズな受け渡し。
これらは人間工学に基づいた、自然な身体の使い方です。
私は、かつてこの仕組みが知りたかった。
けれど、誰もそれを言語化して、ジェスチャー化し、わかるような見本で教えてはくれませんでした。
だからこそ、私はボイストレーナーになり、この研究を続けています。
今回の記事が、あなたが本来の声と再会するきっかけになれば嬉しいです。
「もっと知りたい」「体験してみたい」と思われた方は、ぜひ体験レッスン(対面・オンライン)にお越しください。
参考リンク・動画
●話すように歌う…ボイトレ・歌唱力・話すこと…声の表現の基礎の全てがこの動画に